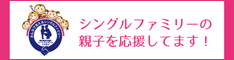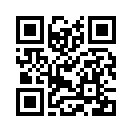「学び」の多様性 ~「既存」に合わせるだけでなく~
2017年04月21日

~集団教育での「学び」~
「社会のニーズ」に対して、育て上げる集団教育。
AIとの共存。「人の仕事」がこれから変化する時代。
今まで通りの教育は、やがて通用しなくなる。
アクティブ・ラーニングが、集団教育では突破口。
しかし、集団教育だけが「学び」ではない。
それが「トップダウン」だとすれば「ボトムアップ」の教育もあるだろう。
ハビリスさんのFBから。是非、動画を見てほしい。
岐阜にも、そんな教育を始めている学校もある。
http://www.u-upkoutougakuin.net/
「自ら学びを求める」生徒にとって、
個々に応じた教育が受けられるだろう。
時間に合わせて動く必要性。
テストの必要性。
カリキュラムの必要性。
…本来の「学び」とは、無縁であっていい。
例えば、図書館での本との出会い。
何気なく手にした本の中に、今までとは違った世界がある。
読み、立ち止まり、自分の中にある価値と比べたり、さらに調べたくなったり…
これも「学び」である。
「学び」は、若い時期だけではない。
坂本龍馬のように、遅い時期に「学び」が始まっても変わる人もいる。
教えている准看護・第二看護受験生の中には、50代の人もいる。
いつでも意欲があれば、学ぶことはできる。
教育を終え仕事に就いた若い人は、どのような状況なのだろうか。
世帯構造別の貧困率(2015年)。計算方法の詳細はhttps://t.co/QtHRu6HiCO pic.twitter.com/3WzpQrsAkP
— 舞田敏彦 (@tmaita77) 2017年4月18日
「若年単身女性の貧困」は、最近話題にもなっている。
「学び」の根底に「貧困からの回避」が、あるかもしれない。
せっかく今まで「頑張って獲得した仕事」を、
簡単にやめるわけにはいかない。
そのため仕事に忙しく、学ぶゆとりもない。
ましてや「世の中のことを考える」余裕もない。
このような現状で、教育の出口が、社会への適応のみとなれば、
大人になり「再び学ぶ」ことに対して、どんな思いになるだろう。
また、自分の子供に「学びとは…」を、
どのように伝えるのだろう。
既存のものを、疑ってみる。
ここからも「学び」が始まる。
スポンサーリンク
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。