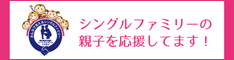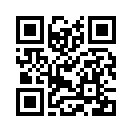鞄の重さ、宿題の量 ~「耐える子ども」をつくるため?~
2017年09月28日

~中学生・肩掛けカバンも消える~
「小1って、こんなに忙しかったですか?」
シングルマザーの親子指導で、母親から出た言葉。
毎日、漢字ドリル・計算ドリルの練習。学期内に3度繰り返しの義務付き。
出来ないと長期休みに補充。教科書音読は家庭で。親の認印がいる。
お子さんは放課後、学童保育で過ごす。最長19時まで。
まず教室で過ごし、宿題をやらないと外には出られない。
さらに暗くなる前に終わらないと、外に出ることはできない。
グランドでは、一旦家に帰った友達が遊んでいたとしても…。
「ランドセルが大きくて、重い。」…次の話題に移る。
教科書のA版化。それに伴いランドセルが大きくなる。
さらにカラーページが増え、紙質もよく、1冊が重い。
中学でも同様。「置き勉禁止」もあり、全て持ち歩く。
中学生の「肩掛けカバン」が見られなくなった。
あのカバンでは、全てを持ち歩くことはできない。
今ではリュックに変わっている。
まるで「登山」に行くかのように、登校する姿を見る。
「耐える子ども」をつくるために…
そんなキーワードが、会話から出てきた。
なるほどなあ、と思いました。子どもの授業を見学して、板書ほぼなし、スライド中心の授業は先生の説明はサッと進むけど子どものアウトプットの時間が多い。発言、グループワーク、個別の作業とそのシェア。授業自体はそれほど早く進まない。授業の力点が違うんだなあ。 https://t.co/4U096vll4A
— 野口由美子 (@noguchi_y) 2017年9月26日
授業においても同様。上記のように海外の教育は変化している。
「子どもに対する姿勢」は、日本特有になっていくのだろうか。
スポンサーリンク
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。