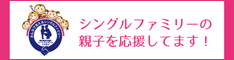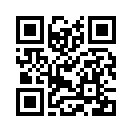リーディングスキルテスト ~進学できる高校の偏差値とかなり強い相関~
2017年11月09日

~教科書の内容が正しく理解できているのか~
「あの時は、お世話になりました。」
塾で受験相談のみで出会った学生に、准看護学校で出会う。
塾に通わないと合格が厳しい人、
塾に通わなくても合格できる人…その差は何だろうか。
塾で教えていて、気付くことがある。
自習用教材の「読み取り能力」の差だ。
自分で読み取れる方は、通塾回数が少なくても塾の効果は高い。
中には、受験相談で「コツ」さえ伝えれば、十分な方もいる。
逆の方もいる。
自分では「読み取れない」
教えてもらっても、その時にはわかった内容が、
自分で問題を解くと、わからなくなる人だ。
塾ではその方でも、記憶に残る方法を見つけ出す。
そして、自分で学ぶことができる状況を作る。
久しぶりに勉強をする方は、そこに時間がかかる。
その上で進学をしなければ、特に看護の勉強は続かない。
看護師になってからも同様。
看護学は「統計学からできている」ので、
常に、よりよいものに更新されていく。
「仕事を続ける」=「学び続ける」となる。
昨日、気になる記事を見つけた。
教科書の文章、理解できる? 中高生の読解力がピンチ https://t.co/DbQZug2Av8
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) 2017年11月6日
中学3年のリーディングスキルテストの能力値によって、
進学できる高校の偏差値がほぼ決定してしまう。
となると、この力が中学で身についているのかどうか。
これからの「学びなおしが多くなる」人生の中で、大切なこととなる。
しかしこのテストに対しては、その時間と設定に問題を感じる。
「評価に関わらない」「単位時間での4択問題」となれば、
意欲が低い生徒は「いい加減に」解答する可能性は否定できない。
この相関結果はそこにも同時に起因するだろう。能力だけの問題ではない。
(能力)×(意欲)=(結果)である。
同一問題が入試で出題されれば、意欲も上がり正答率も上がるだろう。
研究に値する視点ではあるが、このようなテストが定期テスト・学力診断に加えられたらどうなるだろう。
学力診断テスト同様、その対策に追われる授業や演習をする学校も増えるだろう。
まるで教師の事務処理が増えて、
生徒に向かう時間が減ることと同じようだ。
「テストができるかどうかで、能力を測る」
ここから抜け出すことは、出来ないのだろうか。
スポンサーリンク
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。