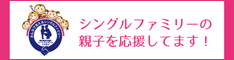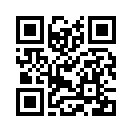小学校の道徳について ~これは何かの冗談ですか?~
2016年01月27日
これは何かの冗談ですか? 小学校「道徳教育」の驚きの実態 https://t.co/76zNCbZcAt
— 現代ビジネス (@gendai_biz) 2016, 1月 25「「道徳」といわれると、多くの人は漠然と「人として良いこと」と考えてしまう。しかし、「道徳」の内容はあまりに曖昧だ。また、法律と違って、誰が作るのかもはっきりしない。このため、「道徳」の授業には、一部の人や集団にしか通用しない規範を、漠然とした圧力で押し付けてしまう危険がある。」
確かに、道徳の内容は誰が作っているのだろうか。
私が中学教師の時にも、考えたことさえなかった。
道徳教育全国大会でも、
文部科学省指導者から、このような話は聞いたことはなかった。
道徳の内容は中学校の場合、4つの「内容項目」において、
その項目にふさわしい読み物を使って指導していた。
ある内容項目の観点からすると「確かに」と思う読み物資料が、
別の観点からみると、「おかしなもの」に感じてしまうものもあった。
このように「ねじれている」という感覚が、その当時からはあった。
しかし「法と照らし合わせる」ようなことは、なかったのである。
「人間関係こそが法」になるかのように、授業をしていたのかもしれない。
教師のときには、「それで当たり前」だと感じていたのかもしれない。
確かに、本文にあるように「学校内道徳が法の支配を排除する」のでは、
「一部の人や集団にしか通用しない規範を、漠然とした圧力で押し付けてしまう危険がある。」
本文最後の言葉。
「法は、人間味のない冷たいものではない。法は、人類の失敗の歴史から生まれたチェックリストだ。憲法は、国家が権力を濫用し、人々を苦しめてきた歴史から、国家の失敗を防ぐ工夫を定めたリスト。民法は、人々の生活の中で生じやすいトラブル集とその解決基準。刑法は、よくある犯罪集とそれへの適正な刑罰の目安を定めたリストだ。」
「法学を学ぶということは、人々の失敗の歴史に学ぶということだ。法には、すべての人の異なる個性を尊重しあいながら共存するための知恵が詰まっている。法は、全ての人を見捨てない。法学に触れて、法の優しさ、暖かさを感じてほしい。」
なるほど と。
スポンサーリンク
Posted by 星野 健
at 00:01
│Comments(0)
│時事
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。