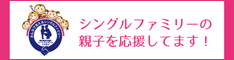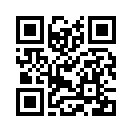通知による激変 ~公立校・不登校児童生徒への支援の在り方について~
2016年10月05日

~変化を感じている方も…~
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」
という通知が、9月14日付で各公立校に。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1375981.htm
「不登校児童生徒数は依然として高水準で推移しており,
生徒指導上の喫緊の課題となっております。」
この「喫緊の課題」に対して、支援の在り方が多様化する。
「場合によっては,教育支援センターや不登校特例校,ICTを活用した学習支援,フリースクール,夜間中学での受入れなど,様々な関係機関等を活用し社会的自立への支援を行うこと」(下記通知より)。やっと,対応が柔軟になってきたね。
— 舞田敏彦 (@tmaita77) 2016年10月2日
この通知は「学校」へ出されているが、保護者には通知されていない。
舞田先生のおっしゃる通り。選択肢は多様な方がいい。ただ、
— 星野 健 (@JUKUHOSHINO) 2016年10月2日
「困ったら丸投げするか」
という形で、学校側のみが判断する場合もあるかもしれない。夜間中学の意味も多様となる。不登校の親も同時にこの通知を認識し、主体的に柔軟に対応することが大切かと。 https://t.co/PdTsDdPsOH
この場合に限らず、
「相手が何を根拠に、どう対応してくるのか。」
それを知った上での対応が必要。
この通知が出たことを、親側も知っておくことからスタートしたい。
その上で、主体的に柔軟に進路対応していくことが、
お子さんのためになると考えられる。
また、yoneさんの指摘は鋭い。
文科省が出した通知は、不登校ビジネスをしているNPOや会社など(夜間中学も含む)の団体が堂々とビジネスができる環境を整えたとも言える。これから、不登校している子どもの保護者は、学校・教育委員会だけでなく、不登校ビジネス業者からの勧誘をどうやってかわすか、気をつけなければいけない。
— yone (@yone_oki5) 2016年9月30日
「活用」「連携」という名のもとに、勧誘が相手側から来るかもしれない。
この点も、要注意だ。
スポンサーリンク
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。