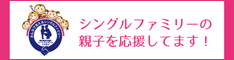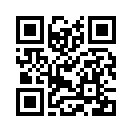教育機会確保法案 ~「問題点のまとめ」から感じたこと~
2016年10月16日

~学校は、どうなるのか~
教育機会確保法案
形を何度も変え、今国会へ提出の流れです。
不登校の子どもが危ない! STOP!「多様な教育機会確保法」 : 10月12日(水)池田堅市さんによる学習会のレジュメです https://t.co/R2wbHwlUmF
— 不登校・ひきこもりを考える当事者と親の会 (@ftkhkk) 2016年10月14日
上記レジュメ、最後の部分より
「今回の教育機会確保法案についての問題点を整理してみたい。
①学びを権利としてとらえず、課程主義的・能力主義的に義務教育制度をつくり変
えようとしている。
②教育機会については、日本国憲法や教育基本法、さらには、子どもの権利条約等
の国際条約等でも規定されているのだから、新たな法律をつくる必然性はない。
③不登校児童生徒を定義することで、不登校を子どもの自己責任に帰しており、い
まの学校のあり方自体を問う視点がない。
④「多様な学びの場」を用意し、子どもたちを分類・排除していく差別制度をつく
ろうとしている。
⑤学校以外の場での学習にも国・地方公共団体の管理が及ぶことになり、多様な学
び、自由な学びは保障されない。
⑥民間の団体が公教育の経営・運営を行うことになり、教育機会の均等性や安定性
に問題が生じる。
⑦子どもの権利条約に則ると謳いながら、子どもたちの意見表明の機会が保障され
ていない。
なお、教育機会確保法案には、夜間中学についての規定も入っているが、それが
まるで不登校の子どもたちの「受け皿」的存在として認識されていく可能性がある。
法案として、別建てにすべきである。」
すべての子供を「管理下へ」という必然性。
そうしたい理由はいったい…
もし、それがあるとすれば何か。
「義務教育留年制」の準備と捉えることも出来る。
義務教育で留年制がない国は、珍しい。
このことを私は、武蔵野大学・舞田敏彦先生のブログで知った。
「データえっせい」2012年12月16日記事より
http://tmaita77.blogspot.jp/2012/12/blog-post_16.html
留年した場合、高校では退学をする場合が多い。
そして、その「受け皿」といて通信制へ。
通信制に通う生徒は、今やかなりの生徒数。全高校生の5%を超えている。
https://twitter.com/tmaita77/status/558397698001231872
(舞田敏彦先生 ツイッターより)
義務教育の場合、留年・退学がない。
小・中で私立の場合、「公立へ」という方法がある。
同公立の場合、何の手立てもない。
その環境を作っていると考えると、上記の➀~⑦・夜間中学の存在が一括で見える。
環境を整えれば、どうなるのだろう。
小・中学校の先生は今、とても忙しい。
「生徒に向き合う」時間以外に、使う時間が増えている。
また、目の前の生徒が「多様である」ことに疲れているように感じる。
そして、この法案が通れば学校は一律に向かう。
さらに留年制を導入すれば…となると、ホジティブに捉える先生も増えるだろう。
それが「いい」「悪い」という価値の問題ではない。
私が「今の流れ」から感じる「次の流れ」への、シナリオである。
スポンサーリンク
Posted by 星野 健
at 00:01
│Comments(0)
│時事
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。