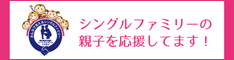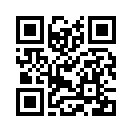手段の目的化 ~京都市「ノート検定」~
2016年12月05日

~私は「ノートづくり」が ダメ なタイプ~
気になるツィートが…
これはノートとらなくてもわかる生徒にとっては、手段の目的化でアホらしいだけだね。自由参加制ならまだ良いけど。→「ノート検定」学力アップにつながる? 京都市教委が試み(京都新聞) - Yahoo!ニュース https://t.co/saNnFUvDHD #Yahooニュース
— あすこま (@askoma) 2016年12月3日
ヤフーの記事が消えていたので、
京都新聞のものを読む
「「ノート検定」学力アップにつながる? 京都市教委が試み」
http://kyoto-np.co.jp/education/article/20161126000045
タイトルに「?」がついていて、少し安心した。
ツイートはさらに続く。
ノート検定の必修化って、学習指導というより教師が生徒を統御する一種の生活指導だよね。例えば、漢字書き取り練習10回の宿題に「もう私はもう全部覚えているからいりません」と生徒が言っても、認められないケースが多いように。
— あすこま (@askoma) 2016年12月3日
とても賢くて偏差値も高いのに漢字テストの成績が悪い生徒たちがいる。これはもう「漢字を手で書く能力は必要ないし、学習のコスパが悪い」と思ってるに違いない。漢字の問題を落としてもどの大学にも入れるから受験勉強も動機にならない。さてどうする?
— あすこま (@askoma) 2016年12月4日
最後の「?」も効いている。
京都が地元の津田先生も、「?」反応している。
文字、図、イラストなどを書くことが困難な子どもたちの評価はどうなっているのでしょうか? 「診断書を出せば検定免除」なのでしょうか? 個別支援計画にこの検定は、どのように活かされているのでしょうか?
— 津田明彦◯臨床心理士 (@akihiko_tsuda) 2016年12月3日
「ノート検定」京都市教委が試み https://t.co/0N6IrVvNaF
ふと、思い出したことが。
私が小学校6年生の時の、担任とのやりとりだ。
自主学習ノートを毎日出すことを、私は目標に決めていた。
ある日、やることが見つからなかったので、漢字練習を2ページやって提出した。
その担任は「C」の評価をつけて返してきた。
「お前はそんなことのために、自主学習を出していたのか」と。
反省した。毎日出すのは辞めた。
「自主」だから「創造的なこと」をしようと。
調べて出しただけでは「B」の評価。
調べたことに対して考察を書くと「A」の評価。
その当時、評価のためにやっていたことが、
それからの自分の癖になった。
本当に、「いい先生」に出会えたと。
スポンサーリンク
Posted by 星野 健
at 00:01
│Comments(0)
│時事
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。