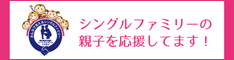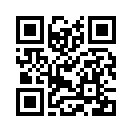岐阜聖徳学園高校・ICT双方向対応 ~オンラインでの学び~
2020年05月09日

~前年度から1人1台iPad~
岐阜県は休校期間が5月31日まで続く見込み。
私が講師をしている岐阜聖徳学園高校では、生徒1人1台iPadを使っている。
前年度から授業でも使っているので、教師もその活用に慣れている。
休校期間でも、学習支援を行うことができている。
http://www.shotoku.jp/gsh/news/0048fbdfb58b7fe9cb0fe6127d0682759b4d031e.pdf
各先生方の動きに、私も刺激を受ける。例えば、ズームによるオンライン二者懇談
http://www.shotoku.jp/gsh/daily-snap/2020/05/152705ict-1.php
そして、ロイロノートで課題ノート添削
http://www.shotoku.jp/gsh/daily-snap/2020/05/150022ictweb.php
「オンライン授業」といえば「手づくり動画」のイメージが強い。
しかし、上記のような双方向・個別対応こそ、今、やるべきことだと私も感じている。
知人より回ってきた、休校期間中の各アナログ・ICT教育の比較表。それぞれのメリット・デメリットの比較がわかりやすい。
— 明日の学校を憂う(西野) (@asujyu) May 6, 2020
今から各学校で動画作成なんて、労力大にして稔りわずか。NHKなどのコンテンツに勝てるはずもない。
学校教員が今やるべきは、双方向での対応だとこれ見れば一発でわかる。 pic.twitter.com/5QYa2bprDx
海外でのオンライン教育は、日本よりかなり進んでいるとのこと。
と言うより、日本は発展途上国並みに遅れている。
自宅にまず「自分が使うPC」がない。
PCを使わない生徒の率。
— 舞田敏彦 (@tmaita77) April 19, 2020
日本は50%。途上国ゾーンだな。
教員が宿題のポスティングに,家を回らないといけないわけだ。 pic.twitter.com/X7m7wccxdy
さらに、デジタル機器を使って創作物を発信することもない。
そう,アウトプットしないね。
— 舞田敏彦 (@tmaita77) April 21, 2020
スマホで面白おかしい記事をRTしてるだけじゃ,頭がトウフになっちゃうぜ。情報の消費者じゃなく,生産者に回らないと。 pic.twitter.com/CA95dxg4h4
具体的に海外との「違い」学ぶために、
海外で暮らした方が主催するフェイスブックのグループに参加した。
「未来の教育シンポジウム FES-Future Education Symposium」
https://www.facebook.com/groups/2581223675484799/
岐阜聖徳学園高校・学習支援の方向性は、グループの中でも評価されている。
スポンサーリンク
Posted by 星野 健
at 00:01
│Comments(0)
│岐阜聖徳学園高校
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。