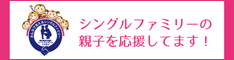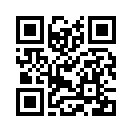折り紙で三角関数のグラフを① ~数の「見える化」により、全体をつかむ~
2016年05月27日

~ことばが映像に、なるかのように~
数Ⅱ 三角関数の授業。
商業科で教えるときに苦労する。
今年は、グラフを「折り紙」で自作し、
それを活用することを思いつく。
ヒントはオーストラリアの数学教育。
自分の「必要レベル」に応じて、学ぶクラスを選択できる。
「数学の証明・考え方重視」「あるものとして活用重視」
の2つから選び、自分の「将来の必要度」に応じて選択する。
「活用重視」の場合、考え方の「流れ」を大事にし、
細かいことは電卓でOK。2桁÷1桁さえ電卓でもOK。
関数電卓は数値だけでなく、グラフまで表示する優れものだ。
ICT化も進んでいる。概要を把握し「使えること」が大事なのだ。
国際調査でも、数学が苦手な人が多い日本人。
他の国がそれほど数学を「苦手」と感じないのも、このためだろう。
逆に、手計算などの「習熟が図られている」ので、テストは日本は国際的にも上位。
国際調査でオーストラリアのような国が順位が下がるのも、仕方がないことなのかもしれない。
http://fundo.jp/64734
数学教育で、日本は「ガラパゴス化」しているのかもしれない。
グラフは数値の「見える化」そのもの。
このブログでよく紹介する舞田先生の「データ・えっせい」も、
まさにその手法だ。
グラフを手に入れれば、現状を把握しやすい。
その「元」になるグラフを、自作することを思いつく。
学びの「成果物」を作り上げ、そこから学びを広げていく。
B4一枚の紙を折り、折り目に数値を書き込んでいく。
書き込むことで、数値のイメージがつかめてくる。
次回は、その作り方について。
スポンサーリンク
Posted by 星野 健
at 00:01
│Comments(0)
│岐阜聖徳学園高校
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。