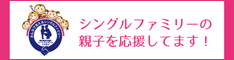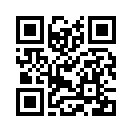今年の准看授業⑤ ~レゴ型・情報編集力・納得解は「KJ法」で~
2015年12月23日

~6人グループによるKJ法~
私自身がKJ法に出会ったのは、大学生のとき。
システム工学演習だった。
ラベルになった情報、各自が持ち寄る。
情報を共有し・編集する。文章化して、納得解を得る。
学生が卒業後、職場で行う看護研究。
夜勤もあり、研究グループで時間がなかなか合わせられない。
卒業生の事情を聞いたとき、
「KJ法は便利で使えるかも…」と、私は感じた。
看護の世界で使えると信じ、
10年以上前から、KJ法を教え始めた。
すると次第に、進学先の第二看護学校で、県内の病院で、
KJ法の図解を見ることが多くなった。使ってくれているのだ。
マナビラボの冒頭の言葉。記事を書いている今、ふと頭をよぎった。
http://manabilab.jp/aboutus
「私たちは信じています。
「今ある現実」を「見える化」できていないものは、具体的に「将来を構想すること」はできません。
「今ある現実」を「見える化」できたところから、生産的な議論がはじまります。」
今年度の授業、仕上げのKJ法では、社会問題について、調べ・考えてもらった。
学生に与えられた時間は、90分が2日+40分が1日でその後すぐ発表。
将来、看護研究をKJ法で行う場合、集まることができる最低限の時間しか与えない。
勤務日・時間帯が違う仕事に就く。集まれる時間に「やることを限定する訓練」のためだ。
ラベルづくりは、普段からコツコツと。
同じホルダーに入れておけば、互いに見合うので無駄なラベルを作る必要がない。
集まって図式さえ完成させてしまえば、それぞれ分担して文章化し、
また、同じホルダーに入れておけば、互いに校正はできる。
しかし、このことを学生には教えない。KJ法を進めていく様子を見守っていると、やはり自然に見付けていく。
「より良い方法を、見付けていこう」という思いを、
摘んでしまうことこそ、私がやってはいけないこと。
私が知っている以上の方法を、見付ける力の方が大切なのだ。
発表では、
現在・シングルマザーであったり、その環境で育った方が語る言葉。
介護施設で介護士として、働きながら通学している方の生の言葉。
『多種多様な社会的背景をもつ人』が、発表内容に深みを持たせた。
あるグループ発表の最後に、印象に残ったシーンがあった。
私たち地方の准看護学生が「何かを言って変わる世の中ではない」と思っています。
(爆笑)
でも、私たちが生きていく世の中を知り、皆さんに伝えることができてよかったと思います。
(拍手)
KJ法をやって、よかったと私も思えた。
経験を積み重ね、思いを持つ。
そして、実践に移す中で少しずつ思いを広げていく。
「目の前にいる人の幸せを願える行動」が、
学生たちはきっと、これからもとれるだろう。
レゴ型…ラベルはレゴのブロック
情報編集力…ラベル拡げ・ラベル集め・表札づくり
納得解…関連図の完成とともに、それはやってくる。
そして、文章化。図解とともに、周囲へ納得解を広げる。
自分の看護観(世界観)を、それぞれが持つ。
KJ法を用いて、世の中へ出てからも是非。
~次回はシリーズ・ラストの予定~
スポンサーリンク
Posted by 星野 健
at 00:01
│Comments(0)
│岐阜市医師会准看護学校
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。