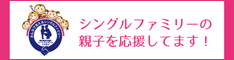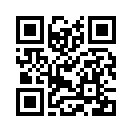点Pの位置を説明する ~数Bベクトル~
2019年11月17日
~後期中間テストに向けて~
塾にて後期中間テスト・数Bの指導。
平面ベクトルまでが試験範囲。
ヤマとなる問題は3つ。
「点Pの位置を説明する」問題は、総合力が試される。
私個人は、ベクトルの問題を解くのが好きだ。
いろいろなアプローチができ、解き方が自由だ。
「始点から終点に向かえば、どんな経路でもいい」
寄り道をしながら、ゴールに向かうのも面白い。人生も同じだ。
しかし、ベクトルが苦手な生徒は多い。
中学・高校を通して物理・力学での「鍛え」が足りない。
理系でも「物理」を選択する生徒は少なく、全高校生の1割程度しか物理を選択しない。
数Bの授業でも、数列を先に教える学校も少なくない。悲しいが、現実だ。
点Pの位置。
始点を「1点」に決め、2つのべクトルの内分・外分により「向き」を確定する。
そしてその長さが「どの程度か」を、内分により文章化する。
その説明文は美しく、無駄がない。その文章を書くことが未だに私は好きだ。
しかし、それを伝えることが難しい。
内分の式への変形・係数の分数が表す「意味」が、
理解しにくいのかもしれない。
伝える技術、まだまだ磨かねばならない。