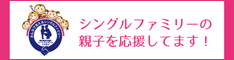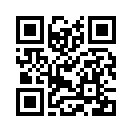オンライン双方向授業を考えたとき… ~小学生の頃を思い出す~
2020年04月25日

~母校は、岐阜市立本荘小学校~
「休校決定94%に 」(朝日新聞)。休校は教育委員会が自ら判断すべきことだ。緊急事態宣言があったから、というのは理由にならない(責任逃れには使えるだろうが)。休校するなら休校中の学習を保障(補償でもある)する手立てをとらなければならない。学習権は人権なのだから。
— 前川喜平(右傾化を深く憂慮する一市民) (@brahmslover) April 25, 2020
オンライン双方向授業を考えたとき、細分化をしている自分に気づいた。
まずは、単元の中での細分化。基本と応用に分け、自宅と学校で学ぶ内容を分ける。
次に、授業の細分化。教授する部分は、既存動画でいい。補足と確認がオンライン双方向授業の中心だ。
「すべてをネット」で、ということを狙うより「対面授業」との区分に、私自身は現在、行きついている。
考えているときに、2人、小学校の恩師を思い出した。
1人は4年生担任のT先生
「終わったら好きにしていいよ」が、口癖の先生だった。終わったら外で遊んでいる友達もいた。
友達と一緒に遊びたいので、私は問題を解き終えたら、次々と男女問わず友達を教え続けた。
そうしているうちに、人による理解の違いを知り、
「どのように伝えるか」の工夫を考えるようになった。
逆に、苦手な図工などは、友達が手伝ってくれるようになった。
父の仕事「紳士服仕立て」が激減した年で、家庭は荒れていたが、学校で私は救われた。
その9年後、私が大学生となったとき、T先生とは「塾長」「バイト生」の関係となった。
工学部学生が「公立学校教師になる」きっかけを、T先生が開いてくれたことになる。
もう1人は6年生担任H先生
とても厳しい先生だった。18時、19時までクラス全員が残されたことも珍しくなかった。
「抜き打ちテスト(予告なしのテスト)」も多かった。それに対しての生徒の批判も多かった。
私はそのころ、テスト前でも全く勉強していなかったので、何の影響もなかった。
「道徳のタイトルづけ」を、月に一度程度させられた。
『資料を先生が読むので、この資料のタイトルを答えなさい』というものだ。
どんな資料か忘れたが「重かった切符」というタイトルを私がつけてから、
褒められると同時に、私への「勉強の質の要求」がきつくなった。
きつい要求を出されたは、自由勉強。
「調べた結果、何を考察したのか」という出口がないと、最高評価「A」をくれなかった。
自然に自由勉強は「歴史」が多くなり、「まだわかっていない」と書かれている内容ばかりを狙っていった。
その頃は、歴史家・磯田道史さんに似ていたかもしれない。
「出口が見えない」とき、根拠・条件を元に考察を重ねていくこと。
小学6年生の私に、「出口を見つける」訓練をしてくれたのだ。「それこそが『学びの出口』だ」と。
根拠・条件設定・考察の1つでもツッコミどころがあると、Aから評価を下げられた。
そして「出口が見えない」ときに、「自分なりの形」をつくる癖を、鍛え上げられのだ。
こんなことを、ふと思い出した。