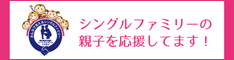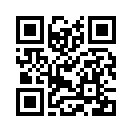一番小さい山が、越えられないときもある

~寄り添い、見守る~
昨日の出来事。
横綱が連敗した。
岐阜聖徳学園高校野球部が、タイブレークで負けた。
過去と比較し「一番小さく見える山」を、越えられないことが人にはある。
私は公立中学教師のとき、ソフトテニス部の顧問をしていた。
夏・最後の市大会の決勝で、自分の学校の1番手と2番手が対戦した。
1番手は2年生秋新人戦から岐阜県で常に優勝、2番手は最高で岐阜地区3位の実力。
その差は大きい。しかし、結果は2番手が勝った。勝負事はこういうことも、よくある。
テストでも同様。たとえば数学の確率。
発想が必要な問題に対し、ひらめいた。
難しい思考過程も通り抜け、表現できた。
しかし最後に約分を忘れた。マーク式・解答のみの採点だと0点になる。
寄り添い、見守る。指導する側は、勝負が近くなると、手出しをどんどん小さくする。
そして勝負当日、一人でも力を出せるようにする。
実際に試合に・答案に向かうときは、ひとりだ。
最後にある小さく見える山。「それを超える時」を、常に意識させていく。
30日 感染状況
可児のジムでクラスターか 岐阜県の感染17人、岐阜高校の生徒もhttps://t.co/CBOqnBcdFg
— 中日新聞・岐阜 (@chunichi_gifu) July 30, 2020
死から生を見る ~①同じことが、違って見える~

~残れた時間からの逆算へ~
昨日の料理は、楽しかった。
個人的には「数学の証明」も楽しいが、それは自己満足で終わる。
料理は「できたもの」が証明そのもの。多くの人に喜こんでもらえる。
ただ作っているときに、これほど幸せを感じたことは、今までになかった。
これはいったい、なぜだろう。
今まで「やりたかったこと」が、久しぶりにできたからだろうか。
確かに、それも感じた。しかし、それだけではない気がする。
昨晩、寝ながらあれこれ考え、探ってみた。
「あと何回、この料理を作るのだろう」…そう思ったとき、ベストなものを目指そうと思った。
過去の経験、特に調理法での使った素材の変化を思い出していた。
この素材、状況がまた揃うことは2度とないかもしれない。
調理以外のことを考えず、集中して取り組めたため、あっという間に時間が過ぎた。
あと何回…残された時間からの逆算が始まった。
そうなったことで、同じことが、違って見えてきたのだろう。
死から生を見ると、「日常」が「非日常」に変わっていくことを意識できる。
「できなくなる」ことが見えてくると、「できている」何気ないことにも、楽しさを感じるのだろう。
今 読んでいる本

~就職する前の高校・大学生に~
今、この本を読んている。
一息ついた時に、まとめて読もうと思っていた本だ。
この本は高校生や大学生にも読んで欲しいんだよなぁ。
— 明石順平@「人間使い捨て国家」発売中 (@junpeiakashi) December 16, 2019
日本には「仕事に殺される」リスクがあるということを若者達によく知ってもらいたい。
法的知識の有無が生死を分けることもある。
脅されて退職できないまま長時間労働で過労死してしまうとか。そういうことが起きるからね。 https://t.co/5chNajFFPy
過労死してまで働く必要はない。
しかし、組織で「頑張る」とその流れに乗ることもある。
前もって知っておく。
その指針となる本である。
根拠となるデータが、しっかりと載っている。
この理詰めの話の進め方も、参考になる。
法的知識が自分を守ることになる。
是非、就職前に読んでほしい。
慣れる ~雨音で起きる~

~早朝に勉強する方も~
強い雨で1時間前に起きた。
先週までは、「何かに気づき」起きることはなかった。
たとえ頭が反応しても、指先以外は動かなかった。
ようやく薬に体が慣れてきたのだろう。
「慣れる」
生活のリズムが変わるとき、
それを待つしかない時もある。
耐えられる部分を乗り越え、新しい「何か」が得られることもある。
看護学校へ通う子育て世代の方々。
この時間には、起きている方も少なくない。
特に実習中は、体と頭が疲れてすぐ寝てしまう。
朝、起きる習慣をつけ、この時間に一人、集中して「自分のこと」をやりきる。
日の出が近くなると「自分のこと」ができなくなる。
家族のために動く「決まったことをする」時間が迫る。
頭が冴えるときに、集中して事を進める習慣が身についていく。
そして、学生生活が終わると習慣は「残り」、「時間」が確保できる。
私もどうやら「時間」を取り戻せそうな気がする。
今日から月曜日まで、時間との戦いとなる。
※ブログはしばらく、不定期更新となります。
考えることに追いかけられて ~多忙な1週間~

~准看護学校授業開始も~
怒涛の1週間だった。
「考えること」に追いかけられた。
目の前の課題に対して、どう対峙していくのか。
薬の副作用で働きが鈍い頭を駆使して、乗り越えることができた。
昨日は、岐阜市医師会のオープンキャンパスがあった。
そこで「岐阜県下進学課程入試対策ミニ講座」が開かれ、私はその講座を担当した。
http://www.city.gifu.med.or.jp/kangoshi/campus/open.html
第1回の講座で「質問が出た内容」を入れ込み、修正を加えた。
一昨日は、岐阜市医師会准看護学校での今年度国語講義が開始となった。
「心理」と「論理」、言葉を通してアウトプットできることを狙う。
毎年のように、少しずつ授業内容を変えている。
今年度は教材とする副読本を代え、その授業づくりを考えている。
塾では、看護入試対策相談・授業が続く。
加えて高校生の期末・AO入試対策が、不定期でこの時期は増える。
特にAO入試は多様で、その対策のために創造的な準備が必要となる。
昨日のAO入試対策のために使った時間は、かなり多かった。合格を願う。
そして先週、正式決定。詳細は後日ブログにて。
11月16日・岐阜聖徳学園高校にて、ICT公開授業の授業者となった。
1年5組「数A」で、ロイロノート使っての公開授業を行う。
http://www.shotoku.jp/gsh/news/2019/09/153041post-99.php
一息つけたので、また「つぷやき」のブログを再開。
自分の足跡を残していく。
再検査の結果 ~中等度狭窄が見つかる~

~本日から、准看土曜授業開始~
8月末に定期健診の結果が出た。
https://nyoki.hida-ch.com/d2019-08-31.html
そして今週、ハートセンターで再検査を行い結果が出た。
最近、自覚される胸の痛みの原因がはっきりとした。
心臓血管の狭窄は、一番悪いところで中等度。
痛みの原因となる血管も特定できた。今のところ薬物療法が選択となる。
今の薬の効果を見るため、トレッドミルを再び行うこととなった。
その結果から薬は見直されるかもしれない。
生まれつきの僧帽弁閉鎖不全もあり、
どちらにも効果がある薬の選択をしていただけるのだろう。
この夏の終わりに、急激に上がった血圧は、
薬の効果もあり、今は収まっている。
今日から、准看護学校での土曜授業が開始となる。
体調を整え、授業が続く12月までを乗り切りたい。
薬を飲み続けることに… ~これから「最も忙しい」時期に~

~12月まで、土曜日の塾は営業時間変更に~
ハートセンターにて、年に1度の定期検診の結果が出た。
結果として薬を飲み続けることになった。
さらに詳しい検査を受けることも決まる。
来週は、そのための時間を取ること・検査結果を聞くこととなった。
生まれつきの持病が、去年・急速に悪化した。
https://nyoki.hida-ch.com/e979426.html
そして、今年はさらに悪くなった。自覚症状もあるようになった。
その原因を探るための精密検査となる。
私は幸いなことに、今まで「飲み続けた薬」というものがなかった。
いよいよ次の段階へと進むことになったようだ。副作用よりも作用が上回る状態となったようだ。
飲み始めた昨日は、薬の作用で今までの自覚された辛さは軽減された。
しかし、それ以上の副作用が意識された。立ち眩みがあり、その後は頭の働きが鈍い状態となった。
時間の経過ともに、副作用の症状は緩和された。
幸いなことに車の運転をするときには、立ち眩みは消えていた。
ただ、頭が疲れているときと同じような状態が続き、高校の授業では、
板書の漢字書き間違えさえ、指摘されないとわからない状態だった。
この週末は、様子を見ながらの生活となる。薬を飲む時間を調整したい。
「置かれた状況の中で、できることをする」
今までもずっと、そうして生きてきた。自営業の部分で調整し、塾の時間を短縮していく。
仕事に支障がないよう、今のパフォーマンス維持に努めるためだ。
9月からは准看護学校での土曜午前授業が始まる。
12月まで「第二看護受験対策授業」を行うことになっている。
そのため、土曜日の塾の営業は休止または短縮となる。
1年で「最も忙しい4か月」を、薬を飲み続け乗り切ることになりそうだ。
※今週末はブログを休止します。
次回は火曜日更新予定です。
事実を検証できる環境が… ~デジタルアーカイブが急務~

~図書蔵書焼却処分~
ツイッターで気になる記事を見つけた。
大きなニュースにならないことが不思議である。
知り合いの作家、栗林佐知さんのツイートがパズる。
恐ろしいよ。歴史が、郷土史が崩壊する。
— 栗林佐知 (@KuribayashiS) August 23, 2019
篤実な担い手だった小中学、高校の先生が殺人的に忙しくなって、図書館司書は立場が不安定で、地方に、史料がどんなに大切か、普通にわかる人がいなくなってく。。。東大や京大の先生だけでは、歴史学はなりたたないのに。
事実を検証するときに、必要不可欠な資料が焼却される。
知的財産に対する感覚を疑う。
ふと、私は岐阜女子大学主催の講演会の話を思い出した。
https://www.gijodai.jp/jyouhou/info/2019/08/2315
作家・脚本家の冲方丁氏は、作家におけるデジタルアーカイブの重要性を語られた。
デジタルアーカイブのおかげで、時短が図れ、若い歴史小説家・SF小説家が誕生しているとのこと。
また、東京大学特任教授の長丁光則氏は、大学図書館について語られた。
北京大学と東京大学の蔵書数は910万冊で同じである。
北京大では、180人の方が蔵書のデジタルアーカイブ化に携わっている。
それに対して、東大ではたったの10人。単純に18倍の年月がかかってしまう。
北京大がデジタルアーカイブを急ぐ理由は、
「大学卒が3億人しかいない」ためだという。
残りの11億人に大学の知識を使える環境を整えるためだという。
東大の姿勢、高知の焼却処分の流れとは雲泥の差だ。
こうなると、デジタルアーカイブは急務である。
アーカイブする内容が重ならないように割り振り、
効率よくデジタル化すれば、後々に役立つデータとなる。
検証できる内容を後の世に残すことが何より大切だ。
働く親を悩ませる 夏休みの弁当 ~東京では~

~「時間があれば」、料理は楽しい~
時間があれば、私は料理を作ることにしている。
自宅にある食材を確認し、足りないものは補充。理屈で考え料理を仕上げる。かなり数学の証明に近い。
最近は「重ね煮」からのアレンジが多い。何より「完成」した喜びを、食べていただく人と共有できる。
自己満足で終わってしまう「数学の証明」と違いは、ここにある。
夏になり、完成した料理にも気を遣う。
カレーでさえも、夏は雑菌がたまりやすい。
さらに「完成してから時間を置いて食べる」弁当に至っては、
この高温多湿の時期から夏にかけて、気を配らないといけない。
働く親を悩ませる 夏休みの弁当、都内学童で共同購入:日本経済新聞 https://t.co/Tk2EUEAm8h「夏場の弁当づくりの手間を減らそうと、保護者会などがネットで手軽に注文できる仕組みを取り入れている」。手抜き弁当は持たせにくいからな。
— 舞田敏彦 (@tmaita77) July 13, 2019
弁当が「共同購入」となれば、同じものを食べることになる。
時間とコストを考えれば、合理的な方法だ。
食べる時間に間に合うように配達されるため、業者の選択をしっかりすれば、
食中毒になる危険性もかなり少なくなるだろう。
東京都では、保護者会がこのような動きを取っている。
東京都では、4月の区議会議員選挙で女性議員が一気に増えている。
「女性公認」が全員当選 地方選で起きた波、参院選では:朝日新聞デジタル https://t.co/U9WX8dJrMN
— 祝日本版パリテ法成立
パリテ・キャンペーン (@parite50) June 4, 2019
女性の政治家が増えると、このような女性の「声」が届きやすくなるだろう。
今後「弁当」がどのように変わっていくのか、注目していきたい。
共働きが多い北欧では、弁当も合理的だ。
「北欧すごい」?驚くほど質素な子どもたちのお弁当(鐙麻樹) - Y!ニュース https://t.co/elCOEE6o5a「ノルウェーの園のスタッフに、日本のキャラ弁やお弁当の写真をスマートフォンで見せたところ、「日本の親はこんなにすごいお弁当を毎日作っているの!?大変じゃない」と驚いていました」。
— 舞田敏彦 (@tmaita77) July 13, 2019
北欧は社会・教育に注目が集まるが、こういう点も注目していきたい。
テキストのみで伝えること ~作家・中村航さんの言葉が響く~

~岐阜県図書館で「美の精華」再放送中~
岐阜放送で放映された「美の精華」が、岐阜県図書館で再放送されている。
第16回 中村航さんの回を見て、その思いに触れた。
「テキストのみで伝えることにこだわる」
「撤退戦を戦い抜いて、小説王になる」
http://backnumber.zf-web.com/binoseika/p1806293531
中村航さんのこの言葉。
引き出したのは岐阜県図書館の笠原明香さんだ。
中村航さんが「どこか別の場所でも話された内容か」と思い検索したが、出てこない。
質問力により、引き出された言葉だと感じた。
その時、作家の栗林佐知さんとツイッターで話したことを思い出す。
栗林さんの言葉「落ち込んでいる人を、小説で救うことかできるだろうか」
それに対する私の言葉「落ち込んでいる人は、小説を読む気力も失せているのでは」
短い文章、音楽、ちょっとした声掛けにより「私は回復した」という記憶を話す。
小説は私の場合、元気な時に効果的だった。
そして栗林佐知さんの短編集は「支援する側にこそ、読んでもらいたいものだ」と感じている。
准看護学校で栗林さんの小説を、生徒のみなさんに読んでいただくのは、そのためだ。
しかし、栗林佐知さんはやはり「あえて挑む」姿勢を貫いている。
ゴールデンウィークだったせいか、いろいろ待っている郵便物がまだ届かない。と思っていたら『吟醸掌篇』が届いた。第22回太宰治賞受賞作家の栗林佐知さん@KuribayashiS編集発行人の文芸誌。とっても楽しみにしていた!栗林さんの『はるかにてらせ』は年初に読んだけど、未だに心の中に脈打っている。 pic.twitter.com/Jq2ZLdiX7b
— Arim (ありむ )絵本『猫のペコリ』 (@ari_m11) 2019年5月7日
今後も小説は脈々と受け継がれ、残っていくだろう。
「テキストのみで伝えること」に全力を注ぐ方々がいる。
それをいかに「読み手」に伝えていくのか。
教育をする側は、そのバトンを渡されている。
吉川さん(大垣北高3年)小説家に 大賞受賞作を出版 https://t.co/1O6gM8l4es #岐阜新聞 @gifushimbunさんから
— 星野 健 (@JUKUHOSHINO) 2019年5月7日