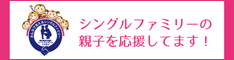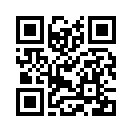岐阜の地域医療は「子育て世代」が支えている ~臨時休校で診療制限も~

~シングルマザーの方も、少なくない現状~
北海道では、3日前に「臨時休校」が決まりました。
そのために、診療制限となった病院があるのです。
新型肺炎で臨時休校 看護師2割の170人出勤できず 帯広厚生病院が一部の診療制限へ(十勝毎日新聞 電子版) (Yahoo!ニュース) #NewsPicks https://t.co/DmCZ9GnyWF
— 平野啓一郎 (@hiranok) February 27, 2020
臨時休校期間が2倍となれば、その影響はさらに大きくなると予想されます。
岐阜県の場合、さらにその影響は色濃く出る可能性も秘めています。
岐阜県の医療は「准看護師」が支えている割合が、他県より大きいのです。
https://www.mjc-nursejob.com/gifu/data/
人口10万人あたりの看護師数が、全国で38位と「少ない」状況を、多くの准看護師が支えているのです。
岐阜市の地域医療は、岐阜市医師会准看護学校の卒業生も支えています。
http://www.city.gifu.med.or.jp/kango/school/index.html
『回答のあった医療機関(病院を除く)で勤務する准看護師、看護師の45.4%が本校の卒業生であるという結果が出ております。』
岐阜市の看護職は子育て世代が多くを占めます。シングルマザーの方も少なくありません。
「医師会の要望」からの「臨時休校」…という情報が出回っています。
しかし、要望書の内容は以下の通りです。
医師会 臨時休校など首相に要望 https://t.co/ryAVhHP8h9
— yuri (@syoyuri) February 27, 2020
しかし、日本医師会の要望書には「患者クラスターや地域の流行状況に応じ、学校医と相談のうえ、地域における学校の臨時休業や春休みの弾力的な設定」とあるだけ。
政府が突如決定した学校の一斉休業にウイルス対策のエビデンスはないと思う。 pic.twitter.com/bGd94U3Pae
医師会は、現状を把握していると考えられます。
全国の自治体及び教育委員会の皆さん。
— 駒崎弘樹 ( Hiroki Komazaki )@病児保育入会キャンペーン中! (@Hiroki_Komazaki) February 27, 2020
政府の一斉休校の「要請」には従わないでください。
中国の約4万5000人のデータからも9歳までの死亡者数は0です。
全くエビデンスに基づいていません。
それより共働き家庭が働けなくなり、医療・福祉が崩壊し、他のところで死者が出ます。 pic.twitter.com/8itZg3Uf93
きっと本当に困っている人がまわりにいないのでしょうね。だから想像ができないのだと思います。 https://t.co/vHMb9zwz9C
— 山根京子 (@wabisabitsuzuri) February 27, 2020
2月21日のブログにも載せた以下のツイート。
これからも人の発言・動きを見るときの基準としたい。
まず必要なのは人権意識
— あの男 (@noiepoie) February 19, 2020
その次に必要なのは手続き論へのリスペクト
最後に必要なのが人間性
サラリーマンも政治家も一緒ですけどね https://t.co/m8Bt3QE9d3
「シャドーのまま」で、学びが進む ~ICTでの私の授業~

~オープンキャンパス講座後の懇談にて~
土曜日、岐阜市医師会看護学校にて講座を行った。
この「岐阜県下第二看護受験ミニ講座」は今年度2回目だった。
今回は、現役学生は少ない状況に感じた。
講座の内容を活かし、合格に結び付けてほしい。
講座後、看護学校のある先生と話す機会があった。
その中で、11月16日・岐阜聖徳学園高校「第1回 ICT公開授業」について紹介をした。
http://www.shotoku.jp/gsh/news/2019/09/153041post-99.php
ICTでの授業を通して「何が変わったのか」を、私は伝えた。
「それがICTの良さなんですね」
「パワーポイントは使う気にならないけど、どんな授業か興味がある」と。
そして「シャドーのままで、学びが進むのですね」
との言葉をいただく。是非、公開授業に来ていただきたいと私は伝え、話を終える。
「シャドーのまま」という言葉。
私の頭に引っかかっていた。
何となく会話の中では、イメージができたが、
看護の世界には「シャドー」という用語があるのだろうとは感じていた。
早速、調べてみた。
「シャドウイング」…看護師の影のように付いてまわり、看護の実際を見学して学ぶこと。
https://www.medicmedia-kango.com/2019/04/17936/
なるほど。確かに私の授業では「最初から最後まで」シャドーでいることが可能だ。
看護実習での出口は記録。そしてのちの看護計画へとつながる。
そのため「シャドー」は、能動的に情報を収集する。そして考えを深める。
「シャドー」の間は、その存在を脅かされることもない。平常心を保つことができる。
「シャドー」なので、「根拠は?」…と、その場で指導者に突っ込まれることもない。
私の授業も確かに同じだ。
学習計画表で「自分の立ち位置」を確かめ、教科書を読むことで始まる。
ICTを用いてポイントの確認と解法の注意点を確認。別解がある場合にはそれを共有する。
課題をそれぞれで解き、ロイロノートで提出。無記名・先着順で黒板表示されるため「誰の解答か」わからない。
ある程度提出が進んだところで、4人班での教え合い開始。
ほぼ同時に「正解」も拡大表示する。自信を持って説明できる状況にする。
早く終わった班は、ワークの問題を解き始める。その中でも教え合いは続く。
全体で確認後、授業は終了。指名・挙手発言・教師の突っ込みは無し。「シャドーのまま」で授業は終わる。
「いつ指名されるのか不安で、安心して授業が受けられなかった」
「間違えを指摘されるのが嫌で、正解が出るまでノートを書かなかった」
「きれいなノートを書くため、説明を聞かずにノートづくりばかりしていた」
ICT授業に転換し「上記のことは気にしなくて良くなった」との声を、生徒の皆さんから聞くようになった。
生徒は「シャドーのまま」になったので、自分のペースで学びを深めるようになった。
この半年で、授業は大きく変わった。そして、授業内での「能動的な学び」が広がった。
11月16日、私は1年5組で「数A」の公開授業。参加申し込みは、下記のリンクから。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQGHMPZz_kGUaB2kFQDWLksbWqTC3w1alddpWP62ad1zx-VA/viewform
FAXでの申込み
2種類のFAX用紙があります。PDFをダウンロードして頂きFAXしてください。
中学生・中学生保護者の方は『中学生・中学生保護者用』をご利用ください。
http://www.shotoku.jp/gsh/news/FAX%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%E7%94%A8%E7%B4%99%E3%80%90%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%83%BB%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E7%94%9F%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%80%85%E7%94%A8%E3%80%91.pdf
小中高大の先生方および教育関係者は『教育関係者用』をご利用ください。
http://www.shotoku.jp/gsh/news/FAX%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%E7%94%A8%E7%B4%99%E3%80%90%E6%95%99%E8%82%B2%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%80%85%E7%94%A8%E3%80%91.pdf
考えることに追いかけられて ~多忙な1週間~

~准看護学校授業開始も~
怒涛の1週間だった。
「考えること」に追いかけられた。
目の前の課題に対して、どう対峙していくのか。
薬の副作用で働きが鈍い頭を駆使して、乗り越えることができた。
昨日は、岐阜市医師会のオープンキャンパスがあった。
そこで「岐阜県下進学課程入試対策ミニ講座」が開かれ、私はその講座を担当した。
http://www.city.gifu.med.or.jp/kangoshi/campus/open.html
第1回の講座で「質問が出た内容」を入れ込み、修正を加えた。
一昨日は、岐阜市医師会准看護学校での今年度国語講義が開始となった。
「心理」と「論理」、言葉を通してアウトプットできることを狙う。
毎年のように、少しずつ授業内容を変えている。
今年度は教材とする副読本を代え、その授業づくりを考えている。
塾では、看護入試対策相談・授業が続く。
加えて高校生の期末・AO入試対策が、不定期でこの時期は増える。
特にAO入試は多様で、その対策のために創造的な準備が必要となる。
昨日のAO入試対策のために使った時間は、かなり多かった。合格を願う。
そして先週、正式決定。詳細は後日ブログにて。
11月16日・岐阜聖徳学園高校にて、ICT公開授業の授業者となった。
1年5組「数A」で、ロイロノート使っての公開授業を行う。
http://www.shotoku.jp/gsh/news/2019/09/153041post-99.php
一息つけたので、また「つぷやき」のブログを再開。
自分の足跡を残していく。
『Most Likely to Succeed』上映会in岐阜
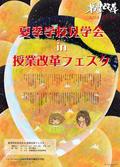
~フェスタでも、話題として取り上げたい~
FBグループの掲示板で、映画のことを知る。
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2183740058413113&set=gm.2562180460480328&type=3&theater&ifg=1
その熱意から、映画を見ることに決め、
交流会にも参加した。
映画を観た。現実に対し、教育を変えていく流れがアメリカでも起こっている。
アメリカのチャータースクールでの教育は、刺激的だった。
既存のカリキュラムを半分以下に圧縮。
各グループでプロジェクトを立ち上げ、発表会までに仕上げる中で学びを深めていく。
選抜されたエリート集団ではない。希望者から抽選で選ばれた生徒。半数は貧困層。
高倍率から選び抜かれた複数の教師の元、プロジェクトは進んでいく。
生徒は主体的に学び、表現を工夫していく。教師は生徒の中にある力を触媒していく。
今までに「無いもの」をつくり上げる創造的な活動は、個々人の力を最大限に引き出すように感じた。
このチャータースクールの大学への進学率は98%
学校全体の成績も、全国平均以上だという。
既存の学校が圧倒的に多い中で、それなりの成果を出している。
卒業生が世の中に出るころ、学校に対する評価が定まっていくのだろう。
日本の大学受験環境も、現在の高校2年生から大きく変わる。
e-ポートフォリオに「学びの履歴」を残していく指導が、高校ではなされている。
それも評価に加味される大学入試もあるだろう。
AOの比率が高くなり、チャータースクールのような取り組みも評価されるかもしれない。
交流会で、岐阜県内公立高校の先生の話が聞けた。
そして、いろいろな立場の方からの思いも聞くことができた。
今のままでは、やはり選択肢は少ない。多様化が必要だ。
学び直しも含めて、いろいろなケースに対応できる場を、私は塾で作り上げていきたい。
主催された大野先生、その奥様。
STAFFとして活動された方々、お疲れ様でした。
このような場を設けていただき、ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします
NHKスペシャル「人体Ⅱ」 ~トレジャーDNAを探る~

~教育が変わる可能性も~
NHKスペシャル「人体Ⅱ」 あなたの中の宝物~トレジャーDNA~を観た
令和の幕開けと共に始まる、新シリーズ!
— NHKスペシャル公式 (@nhk_n_sp) 2019年5月5日
タモリ×山中伸弥の「シリーズ人体Ⅱ遺伝子」
「がんを防ぐ力を高めるDNA」
「認知症を抑え込むDNA」
「老化を抑えるDNA」、
あなたの中にも“トレジャーDNA”が眠っているかもしれない。
こんや9時です!https://t.co/wFbCx0ti5q pic.twitter.com/bXPkZ6AQg7
トレジャーDNAを見つけ「それに合った生き方」が自然であること。
そして平均70個もの「突然変異遺伝子」を、人それぞれが持っていることに驚いた。
基礎教育は一律平均的なものでもいい。
しかし、高等教育への接続時には「自分に合ったもの」すなわち
「感覚的にわかること」を見つけることが重要だと感じた。
多くの失敗から「自分に合ったものを見つけだせる」といいだろう。
1週間で10万円で作ったものなら、違うと分かった時点ですぐ捨てられる。
— 吉藤オリィ@新著書「サイボーグ時代」発売中 (@origamicat) 2019年5月2日
1年かけて1000万円投じてしまったら、後で違うと気付いても簡単には捨てられず、生まれた成果をなんとか役に立たせようと更にコストをかけてしまう。
初めから上手くいく奴なんかいない
大量実験、大量失敗の癖を身に付けろ
自分自身のトレジャーDNAを感じるのも、同じだろう。
短期間に多くの失敗をし、苦も無く成功できるもの見出だし、
そこに自分の能力を集中させればいい。
あとは「ギリギリのいいかげん」でも過ごせればいい。
Nスペ「人体」シリーズは、毎回驚かされる。
しっかりした根拠・事例が紹介されるのがいい。
新たな事実から、自分自身の考えを更新していく。
それが「教育にどう反映できるのか」…考え続けていくのが楽しい。
東大入学式式辞 ~読んでいただきたい内容~
~環境により、飛べる範囲も変わる~
上野千鶴子氏の式辞。ぜひ全文を読んでほしい。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/president/b_message31_03.html
1文が短く、ストレートに内容が伝わる。
そして、前半の女性にかかわる話が印象に残る。
「がんばったら報われるとあなたがたが思えることそのものが、あなたがたの努力の成果ではなく環境のおかげだったこと忘れないようにしてください。」「恵まれた環境と恵まれた能力とを恵まれないひとびとを貶めるためにではなく、そういうひとびとを助けるために使ってください。」@ueno_wan
—(@mlookslike_) 2019年4月12日
このことは、切に願いたいことだ。
私はこの4年、シングルマザー看護奨学生プロジェクトを行ってきた。
4年間で25名の方が、このプロジェクトを通して看護職への道を歩まれている。
1期生・2期生の方は、この春から看護師・准看護師として就業された方もいる。
子育てを「ひとりでしながら」の資格取得。その努力は並大抵のものではない。
離婚すると、男性とは違い、女性の場合は置かれた環境が激変する。
看護奨学生の方々は、結婚・出産により、今までのキャリアが失われた方ばかりだ。
再就職で「一人で仕事をしながら子育てもできる職種」は、限られている。
「環境」が恵まれていないのである。
看護学校に合格すれば、ひとり親支援が受けられる。
しかし、合格するまでは、支援を受けることができない。
また、自分が「どの学校なら、合格できそうか」という情報も得られない。
そこを補うためのプロジェクトを、私は続けている。
「合格」すれば、環境は変わる。
公的な支援により「学び」に専念することができる。
「やってみよう」「なんとかなる」「自分らしく」…ほとんどの方が卒業まで頑張る。
環境が変わりゴールが見えると、その力は最大限に発揮される。
少なくとも実家があって、お金が出せて、レベルの高い偏差値を維持できる状態にあった皆さん。決して万人が手に出来るものではないです。だから、恵まれていると自覚して欲しい。そしてノブレスオブリージュの思想で、ぜひ社会に還元して欲しいです。 https://t.co/KEu2iyOYew
— みなみ 海 (@cocoro_zasi) 2019年4月12日
現在、【第5期】シングルマザー看護奨学生を募集中。詳細は下の入り口から。
https://reserva.be/hoshino/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=24eJwzMzS1AAACEQDV
教育とは触媒である ~自己肯定感を高めて、次のステージへ~

~反応を促進し、引き出していく~
ITC教育について今、個人的に学びを進めている。どうやら「個別化」へ行きつくようだ。
挙手発言・指名・ノートづくり・小テスト…それを無くすことも可能となる。
そうなると、それを評価することもなくなる。「学ぶ過程の記録」と「中間・期末」の2つからの評価となる。
今までの積極性・字の綺麗さ・カラフルな書き込み…確かにどれも学びの本質ではない。
挙手発言。私も中学の時「苦手」だった。
出来る限り、手を上げずに済ませたかった。
みんなが分からない・発言がない時に、よく指名された。
突然の指名で気持ちが揺らぎ、うまく表現ができないことが多かった。
ノートづくり。私はルーズリーフをファイリングして使っていた。鞄が軽くて済む。
きれいにノートを作らないと…という強迫的な思いは持ちたくなかった。
なので、問題演習の跡と「忘れそうなことの記録」しか書かなかった。他人から見れば落書きだ。
「自分が後で振り返ったとき、分かればいい」という思いしかなかった。
なので学校の先生からの評価は低かった。当然のように学校での成績は、
同じ学校群を受験した生徒の中では、一番低かったと記憶している。
しかし高校に入学した後、余分な苦労はなくなった。
座席順での指名、テストでの評価が主体となったからだ。
手段さえ変わってしまえば、
「勉強そのもの」とは関係ないことは、
考えなくて済むこととなる。
当然、気持ちが揺らぐこともない。
手段から解放された生徒は「学びそのもの」に、アプローチができそうだ。
「ありのままの自分」をノートに残し、配信された内容で、いつでも確認ができる。
双方向のやりとりで、先生と仲間と学びを深めることもできる。
授業に欠席した場合でも、配信による記録で、いつでもどこでも学ぶことができる。
「教育とは触媒である」
教師になる私へ、大学ゼミ恩師からブレゼントされた言葉だ。
良いものを引き出し、自己肯定感を高めいてく過程をサポートする。
テクノロジーの進化により、より本質的な方向へと教育は変えられる気がする。
教員免許更新が「永遠」とは… ~逃げ切った人たちとの違い~

~教員不足に拍車が~
更新された教員免許証明が届いた。
そこに、次の更新時期が書かれていた。
「平成41年3月31日」
存在しない更新日だが、63歳でまた決断が必要なようだ。
講師をしている高校の職員室で、免許更新が話題となる。
更新が「必要のない」逃げ切った方々と、
永遠に「更新が必要」な私たちとの差がはっきりした。
教員不足の補充は「講師で」と考えても、意識しないと免許は失効しいるのである。
広島県内35校で教員不足 授業できない学校も(RCC中国放送) - Yahoo!ニュース https://t.co/aocOP13SUF @YahooNewsTopics広島、島根、神奈川県、教員がブラックなのが知れわたりなり手がいない。超絶激務という。残業代無し、代休無し。
— 新(職業としての教員) (@VtXV5Y8EeIcyB6I) 2018年5月16日
若くて優秀な奴は教員目指さない。
— ぶつりのせんせい (@phy_jm) 2018年5月20日
というか、若くて優秀な人間も居るけど、それが少なくになっちゃって、若くて優秀な人だけで定員を埋められなくなってる。
既に若い人に憧れられる仕事じゃなくなってる。昔からあるキツイ汚い危険の3Kな面ばかりがクローズアップされちゃってる。 https://t.co/OQky9RQgMW
「臨時免許を出すから」
という誘い文句が、私たちを襲う事態になるのだろうか。
もしそうなら、更新自体が無駄になる。
何とも不思議なことが起こりそうだ。
【8時15分更新】「生きがい」を見つける場を ~NPO賛助活動~

~NPOの設立趣旨に沿った活動へ~
3月3日 NPO設立総会のため東京へ行った。
http://nyoki.mino-ch.com/e45151.html
その前に、ネットを通して「自己紹介」をした。以下がその内容。
http://nyoki.mino-ch.com/e44357.html
「生きがいについて」
これが私の卒論のテーマだった。職種・役職において、
「『仕事・家庭・余暇』のどれに対して、生きがいを感じているのか」
を調査した結果を分析し、考察を入れてまとめた。
そしてその研究結果が、のちの人生を考えるきっかけとなった。その結果、
「多くの人が歩まない道」を選択し、その中で生きていくことを繰り返した。
名工大卒なのに、企業に行かず教育職へ(その年の卒業生で、たった一人だった)。
『安定の公務員』を10年で辞め、自営業へ。『レアな人』の生き方を、自らの判断で歩み続けた。
『自分の時間』を得て、
「生きがい」を元に、
仕事をその都度選択した。
そして、今がある。
2018年、55歳を迎える年に、NPO法人設立にかかわることになった。
新設される『NPO法人しーそー』の、副代表理事になることに決まった。
塾ではその設立趣旨に沿った活動をする。4月中旬から高・大生、社会人向けに
『生きがいのある働き方』を、探す場をつくることに決めている。
AIとの協働、副業容認という「新しい働き方」が求められる時代。
『過去と同じ生き方』で、『一生同じ仕事を続けられる人』が、今後は『レアな人』になるだろう。
人生が100年も続く時代となり『仕事よりも自分の方が長く生きる』ことになる。
私のような『レアな人』の生き方が、これから『多くの人』の生き方になるのだろう。
高齢化ニッポンを支えるフリーランスという働き方……日本ではスキルに繋がる副業の実施率がかなり低い(舞田敏彦)https://t.co/XqVsXO4QKy#フリーランス #副業 #働き方 pic.twitter.com/EARGGL1hoV
— ニューズウィーク日本版 (@Newsweek_JAPAN) 2018年3月9日
『会社に依存し続けて個人での稼ぎ方を知らない人は、定年後に苦労することになるだろう。副業をして、どこででも通用する汎用性のあるスキルを身に付けることも重要だ。収入を増やし、新たなスキルを習得する観点から、政府も正社員の副業を推奨する方針を示している。』
私の塾は、時代とともに変わる。しかし基本は変わらない。
生きがいを見つけ、『必要な時に、必要なことを』一緒に考え、
解決に向けての方向を探り続けていく。
3月下旬にはその活動が発表出るように、準備を進めていく。
社会が用意したレールに乗るか、乗らないかで、子どもや家族の心を萎縮させて、想像力を奪い続ける社会が、失敗を恐れるだけの面白味のない人生しかおくれない人たちを量産している。
— 津田 明彦 (@akihiko_tsuda) 2018年3月8日
社会が用意したレールをみんなで奪い合うのではなく、「あなた専用」のレールをあなたのペースで楽しみながら走ることが「幸せな人生」だと思いませんか。
— 津田 明彦 (@akihiko_tsuda) 2018年3月8日
いじめ、ハラスメント、虐待など、支配にみちた社会の中で「個性」「自由」「対等」を大切にする生き方をサポートする【NPO法人しーそー】設立準備中ですが正会員(現在18名)・賛助会員(現在3名)を募集中です。詳細はLINE(QRコード)又はDMにてお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願い致します。 pic.twitter.com/edsDNQCGSv
— 津田 明彦 (@akihiko_tsuda) 2018年3月11日
高校で伸びる生徒 ~「考える」習慣が、未知の問題解決に~
~鉢の中では、限界が…~
岐阜聖徳学園高校での学年末テストが終わった。
私は高校で数学の講師をしているので、当然のように採点をして、成績を付ける。
そして1年間の個々の変化を見る。
そんな中で、目覚ましく伸びていく生徒もいる。
その生徒は当然のように、習ったことの基礎知識はある。
知識を「発展的に活用できる」ようになり、目覚ましい伸びとなったのだ。
考える習慣が「未知の問題に向かい、解決していく力」になる。
「既習事項の再生」だけでは、世の中でも対処できないことがある。
塾においても同様だ。
目覚ましく伸びるための「環境」をつくり、「その力を引き出していくのか」を個に応じて考える。
「自分で考え、努力する部分」は、家庭学習に任せている方もいる。
そういう方は、自分の必要感が高まった時に、ネット予約をして通塾する。
塾の卒業生で、高校の定期テスト前だけに通う人がいる。
授業内容で理解しようとする努力が、普通に身についている。
わからない内容が、具体的ではっきりしている。
短期間でも、内容の濃い学習になる。
看護入試の直前で、小論文や数学にターゲットを絞って通う人もいる。
特に、不合格が続いた人のやる気はすごい。
その必要感から習熟までの努力が凄まじい。
2~3週間の集中特訓でも、内容の濃い学習となる。
社会人で、仕事が休みの時だけ、月に2回程度通う人もいる。
仕事で疲れたあと、または、休みに集中して独学する癖が付いている。
「勉強に専念できることがレア」なので、思い出すことに苦しい時もあるだろう。
考える習慣がついてくると「勉強が楽しくなる」という。
自立している人は、適切な目標を設定し、環境を整え、最大限努力する。そして、
やがて根元が、乾いてくる。すなわち「自分だけでは、解決できない」状況になる。
「水が欲しい」という状態で、通塾する。塾での学びを通して、
見方・考え方を修正し…水がしみ込むように、理解がすすむ。
そういう方は、渇いた分だけ、土に強い根が張れている。
自分で考える習慣が身についているので、目覚ましく伸びていく。
「見たことのない新しい課題」に対しても、仮説を立て、解決に向かう癖がついている。
入試・資格試験などに強くなるのは当然の結果。通塾回数が少なくても、結果に結び付いている。
身についた力は当然、「次の学び」にも、生きていく。
入学前に身についている人は、やはり強い。
高校生の場合、学年が進むにつれその「伸び」に、勢いがついていく。
高校で伸びる生徒は、自立し、考える習慣がついているので、未知の課題にも対応できる。