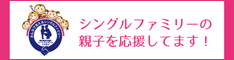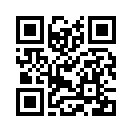【第6期】塾・シングルマザー看護奨学生候補1人目決定

~一次面接は5月20日まで~
本日、【第6期】シングルマザー看護奨学生候補の1人目が決定しました。
岐阜市外在住、看護助手として働いている方です。
推薦入試を目指し、小論文対策を開始することになりました。
この方は通塾しない方法で、しばらくは学習を進めます。
シングルマザーの方で、塾にて看護受験支援を受けたい方は、
今年度から、申し込み窓口が分かれています。
岐阜市在住の方は、岐阜県ひとり親家庭等就労・自立支援センターで、
「准看・看護学校等受験対策個別支援」講習の申し込みができます。
http://shien-gifu.sakura.ne.jp/kousyukai-oshirase.pdf
問い合わせ先 岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター
電話(058-268-2569) 月~土曜日 午前 9 時~午後 5 時(祝・祭日を除く)
岐阜市外在住の方は、塾での看護奨学生候補として通塾できます。
【第6期】シングルマザー看護奨学生候補・第一次募集は5月20日まで。
ネットにて、面接予約をして下さい。
https://nyoki.hida-ch.com/e1057318.html
このように、岐阜市外在住の方も、塾にて
今年度も、例年通りの支援を続けています。
4月29日の記事
~いつの日か、振り返るために~
矛盾という言葉がある。それを感じたことが1日の中で起こる。
この事実に対して、いつか答えが出る時があるだろう。
私には今、その答えはみつからない。
そんなときは、あとで振り返るために矛盾を感じた事実を残しておく。
今日で、5日連続岐阜県では「感染確認者数」が0であった。
岐阜県と岐阜市で新規の感染者ゼロ、5日連続#新型コロナウイルス #COVID19 #coronavirus #岐阜https://t.co/4GamrAlCEP
— 中日新聞 (@chunichi_denhen) April 28, 2020
ニュース見出しでは「感染者ゼロ、5日連続」と書かれている。
本日の検査数(退院の陰性確認除く)は5件、陽性結果0名、陽性者率0%で四日連続です。あくまで2週間前の状態であり、油断大敵。引き続き警戒して下さい。GWは外出を自粛し、人との接触を避けて下さい。陽性患者72名(-)、退院28名(+4)、転床0(-1)、死亡4名(-)退院された方、ご快癒何よりです。
— 柴橋正直 岐阜市長 (@shibahashi_m) April 27, 2020
岐阜市長は、危機感を持ち続けている。「検査数」とそれに対する「陽性結果」と書いている。
さらに、岐阜高専の判断には驚いた。
https://www.gifu-nct.ac.jp/
5月11日を対面授業による開講予定日としておりましたが、
岐阜県、愛知県における感染拡大の収束が見通せないことなどから、
遠隔授業を本格的に実施します。☛その期間は、8月7日まで。それまで対面授業はない。
東京都と大阪府の新型コロナウイルス感染症患者の全数プロットと人口ピラミッド。2020年4月21日更新。公開されているデータを図に変換したものです。それぞれの図はスケールが違うので見た目の比較はできません。これをみて特定の属性や集団を非難されないようくれぐれもご留意ください。 pic.twitter.com/XvCHU69Xwa
— SUGIMOTO Tatsuo 杉本達應 (@sugi2000) April 22, 2020
就労支援講習会・受講者募集 ~岐阜県ひとり親家庭等就労・自立支援センター~

~「学ぶ」ことで、未来を変える~
これは戦い。ステイホームと書くよりしっくりくる。 pic.twitter.com/gVJ0ypBWWF
— Rie (@rienova) April 25, 2020
新型コロナウイルスのニュース・情報に、毎日心が痛む。
またこの2日間は、その影響によるTwitterでの話題に、心が痛む。
まず人権。そこから考えると、阪神・淡路大震災を経験した安先生の言葉に行きつく。
『心のケアって…今
— Akemi (@kemi7a) February 8, 2020
わかったわ
誰もひとりぼっちに
させへんって
ことや…』
#心の傷を癒すということ#最終話#安先生#柄本佑さん pic.twitter.com/APVsrZm030
「誰もひとりぼっちにさせへん」…それは「誰と、どのように結びつくのか」に、大きく影響される。
私たちの要求を取り入れる形で、住居確保給付金や生活保護を使いやすくしてセーフティネットを拡充する。この間の厚労省社会・援護局の動きには目を見張るものがあります。各政党や政治家、メディアは一連の改革を支持し、更なる進化を促してほしい。間違っても制度利用者のバッシングなどしないように
— 稲葉剛 (@inabatsuyoshi) April 24, 2020
厚労省通知により、窓口の動きも変わってきている。
また「学ぶ」ことで、未来は変えられる。令和2年度 就労支援講習会の案内
(岐阜県ひとり親家庭等就労・自立支援センター)
http://shien-gifu.sakura.ne.jp/koushu.html#moushikomi
募集期間が5月15日までとなっているので、早めに動いてほしい。
これから大型連休に入る。実際に窓口が開いている期間は、さらに短い。5月15日まで、あと半月。
http://shien-gifu.sakura.ne.jp/kousyukai-oshirase.pdf
申込書類は郵送で受け付けている。まずは、電話で問い合わせることから始めたい。
○問い合わせ先 岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター
電話(058-268-2569)
月~土曜日 午前 9 時~午後 5 時(祝・祭日を除く)
塾での支援についても、第一次募集は5月20日まで。
https://nyoki.hida-ch.com/e1057318.html
リーマンショック後に、看護受験倍率は急激に上がった。
今年度准看護・看護受験状況は、私も予想がつかない。早めに備えておくのが無難だ。
岐阜聖徳学園高校5月31日まで休校 ~学習支援計画づくり~

~岐阜県の判断は早い~
私が講師をしている岐阜聖徳学園高校の休校が、5月31日まで延長となった。
http://www.shotoku.jp/gsh/news/2020/04/145303427.php
先週からスタートした学習支援は、今後も続くこととなった。
https://nyoki.hida-ch.com/e1058102.html
学習支援の方向は、学校全体で決まっている。
http://www.shotoku.jp/gsh/news/2020/04/142155413-1.php
「① 授業(課題)の配信や指示」「② 課題の提出」「③ 提出された課題への評価(コメント)」
の3つを、1つのパッケージとした学習支援となっている。
私の場合、現在のスタイルは以下の通りだ。
①は、Classiによる動画視聴とその後の確認問題で学習状況を把握
②で、教科書「練習」を解いてロイロノートで提出。上記状況により補足説明を事前に配布。
③は、ライブ授業で課題評価・返却、質問の受付と返答。すべてロイロノートで行う。
単元を通しての見通しを立てるために、5月末までの学習計画表を作った。
基礎的な内容に絞り込み、単元全体を見通して学ぶ形に変えた。
応用例題など、多くの知識や説明必要なもの、別解があるものは学校で扱う。
「仲間との学び」が、より効果的なものは、後で扱ったほうがいい。
数日間の授業を通して、感じたことがある。
質問をカードにして、送ってくる生徒が多いことだ。
そのカードに対して補足説明を書き込み、クラス全体にその「質問と答え」を広げていく。
ライブでこれを行う教師は、とてもハードな作業となる。話をせず、カードにその解答を書いて返すからだ。
この苦労を通すことで、現在、対面授業とほぼ同じ手ごたえを感じている。
今年は同じ授業を5クラスで行っている。
話しただけでは、その内容は「消えてしまう」が、カードに残せばその内容は「手元に残る」のだ。
つまり、そのカードを使って後のクラスでの質問にも、応じることができる。
前に書いたように、今やっていることは「次善の策」という想いは、さほど変わっていない。
確かに、対面授業・教え合いの良さをさらに強く感じることの方が多いくらいだ。
しかし、一度も会っていない生徒がこれほど生き生きと質問をし、その返答に応えてくれる。
その新たな驚きと喜びが゛、今の苦労を支えている気がする。
今日の失敗を反省し、改善し、より良いものに変えていく。
新規採用で働いたころの気持ちが、こんな形で蘇るのも不思議な気がしている。
オンライン双方向授業を考えたとき… ~小学生の頃を思い出す~

~母校は、岐阜市立本荘小学校~
「休校決定94%に 」(朝日新聞)。休校は教育委員会が自ら判断すべきことだ。緊急事態宣言があったから、というのは理由にならない(責任逃れには使えるだろうが)。休校するなら休校中の学習を保障(補償でもある)する手立てをとらなければならない。学習権は人権なのだから。
— 前川喜平(右傾化を深く憂慮する一市民) (@brahmslover) April 25, 2020
オンライン双方向授業を考えたとき、細分化をしている自分に気づいた。
まずは、単元の中での細分化。基本と応用に分け、自宅と学校で学ぶ内容を分ける。
次に、授業の細分化。教授する部分は、既存動画でいい。補足と確認がオンライン双方向授業の中心だ。
「すべてをネット」で、ということを狙うより「対面授業」との区分に、私自身は現在、行きついている。
考えているときに、2人、小学校の恩師を思い出した。
1人は4年生担任のT先生
「終わったら好きにしていいよ」が、口癖の先生だった。終わったら外で遊んでいる友達もいた。
友達と一緒に遊びたいので、私は問題を解き終えたら、次々と男女問わず友達を教え続けた。
そうしているうちに、人による理解の違いを知り、
「どのように伝えるか」の工夫を考えるようになった。
逆に、苦手な図工などは、友達が手伝ってくれるようになった。
父の仕事「紳士服仕立て」が激減した年で、家庭は荒れていたが、学校で私は救われた。
その9年後、私が大学生となったとき、T先生とは「塾長」「バイト生」の関係となった。
工学部学生が「公立学校教師になる」きっかけを、T先生が開いてくれたことになる。
もう1人は6年生担任H先生
とても厳しい先生だった。18時、19時までクラス全員が残されたことも珍しくなかった。
「抜き打ちテスト(予告なしのテスト)」も多かった。それに対しての生徒の批判も多かった。
私はそのころ、テスト前でも全く勉強していなかったので、何の影響もなかった。
「道徳のタイトルづけ」を、月に一度程度させられた。
『資料を先生が読むので、この資料のタイトルを答えなさい』というものだ。
どんな資料か忘れたが「重かった切符」というタイトルを私がつけてから、
褒められると同時に、私への「勉強の質の要求」がきつくなった。
きつい要求を出されたは、自由勉強。
「調べた結果、何を考察したのか」という出口がないと、最高評価「A」をくれなかった。
自然に自由勉強は「歴史」が多くなり、「まだわかっていない」と書かれている内容ばかりを狙っていった。
その頃は、歴史家・磯田道史さんに似ていたかもしれない。
「出口が見えない」とき、根拠・条件を元に考察を重ねていくこと。
小学6年生の私に、「出口を見つける」訓練をしてくれたのだ。「それこそが『学びの出口』だ」と。
根拠・条件設定・考察の1つでもツッコミどころがあると、Aから評価を下げられた。
そして「出口が見えない」ときに、「自分なりの形」をつくる癖を、鍛え上げられのだ。
こんなことを、ふと思い出した。
休校 5月31日まで延長へ

~岐阜県内全域への知事要請~
5月31日までの休校措置
岐阜市内小・中に続き、県内公立高校も決定となった。
https://mainichi.jp/articles/20200424/k00/00m/040/215000c
それに私立高校も合わせていくと考えられる。
現在行っている岐阜聖徳学園高校オンライン学習サポートは、今後も続くことになる。
以下は文部科学省4月10日の通知
学校が課した家庭学習が以下の要件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、
十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと学校長が判断したときには、学校の
再開後等に、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることができること。
<要件>
① 教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること。
② 教師が当該家庭学習における児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握する
ことが可能であること。
ここを意識しての指導計画・学習状況及び成果を把握した跡を残すことだ。
Classiでの事前動画配信後のの確認テストで、理解度は図ることができている。
前年度と同じ学年・コースを担当しているので、私自身が理解度の比較もできる。
ロイロノートを使い、学習サポートを行い演習・質問の時間をできる限り確保し定着を図る。
すべての記録は、データとしてiPadに残るので、特に個人記録をまとめる必要はなさそうだ。
ICT環境が整っているおかげで、この現状において、
「本来、力を入れたい部分」に集中して取り組むことができている。
各家庭でバラバラに過ごしている生徒が、同じ時間に同じ課題を取り組んでいる。
「一人じゃない」…この思いを持ち学び続けることを、岐阜聖徳学園高校の生徒はできているのである。
http://www.shotoku.jp/gsh/news/%E8%87%A8%E6%99%82%E4%BC%91%E6%A0%A1%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%B8%AD%E3%81%AE%E5%AD%A6%E7%BF%92%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%801%E3%83%BB2%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%80%85%E7%94%A8.pdf
4月22日の記事

~落ち着いたときに、振り返るために~
いろいろなことが、同時に起こる日だった。
個人的には、オンライン双方向授業・そしてその準備で忙しかった。
次々と飛び込んでくるニュースを見て、それぞれ「考え方の違い」に驚いた。
落ち着いたときに、振り返るために記事を残しておく。
「10万円」について
世田谷区の保坂展人区長(64)が20日、ツイッターを更新。5月から実施される政府の10万円給付について問題点を指摘した。https://t.co/zq5v4f0Fuu
— 保坂展人 (@hosakanobuto) April 21, 2020
県職員の10万円は知事のものではないので「活用」しちゃまずいと思います。でもこういう「世帯主」はいっぱいいると思いますよ。世帯主ではなく個人に直接渡すべきです、ホントに。https://t.co/6HR0qZDg3K
— 想田和弘 (@KazuhiroSoda) April 21, 2020
10万円、私は申請して、全部地域で消費させていただきます。申請しないと国庫に溶けてしまうだけ。本来、和光市には来ないお金なので、全額きっちり市内で使います。時節柄、飲食店のテイクアウトかなあ。タグ作ってみました。#10万円の使い道 #10万円もらう政治家
— 和光市長松本武洋@日々是手洗い (@takeyanm) April 21, 2020
「マスク」について
昨日、非常勤講師をしている岐阜聖徳学園高校で布マスクが1枚配布されていた。
教師用に国から配布されたものだという。
確かにサイズは小さめで、私が使うと鼻が出そうだった。
厚労省が妊婦向けマスクの配布をいったん停止 不良品7870枚
— 盛田隆二
アベノマスクのメーカーは非公表。政府はなぜこんな杜撰な製造元や製品情報を隠蔽するのか? これが企業なら466億投じた担当役員は更迭、社長のクビも危ない。つまり加藤は更迭、安倍も責任が問われて当然の事態だhttps://t.co/9fPTdNc7XyMorita Ryuji (@product1954) April 21, 2020
原因を考えている人もいる。
アベノマスクはカビが生えていたり変色していたりする。つまり古い。とすれば、以下の「10年前の備蓄」である可能性は高いのではないか。https://t.co/E6PTynQBXV
— 本田由紀 (@hahaguma) April 21, 2020
それを点検もせず配ったこと、それと配布費用との関係について、国民に健康被害や公費支出のダメージを与えた政府は早急に説明しなさい
アベノマスク。残りの金はどこに消えたのか?466億円の行き先はしっかりと公開する義務が政府にはある。まさか、まさかオリンピック延期のために投入されたか?
— 清水 潔 (@NOSUKE0607) April 21, 2020
なんて、腹を探られたくないでしよ。きちんと説明を求めたい。 https://t.co/QGtAVdTQ6T
オンライン教育について、考えさせられる記事にも出会う。
仏、コロナで拡がる教育格差
— 今井紀明 寄付で経営するNPO代表 (@NoriakiImai) April 21, 2020
・仏、オンライン授業で教育格差が発生。5~8%が教育現場から離脱。
・家庭環境やモチベは十人十色であり、より良い学習環境を整えるのは難しい。
・政府、地域の連携で勉強が遅れた学生をサポートしきれるか。
https://t.co/icJQdpMkTF @japan_indepthさんから
原油先物取引価格も含め、「過去にない状況」が短期間で次々と起こってくる。
こんな時こそ、フォトジャーナリスト・安田菜津紀さん言葉を、心にとどめておきたいと感じた。
フォトジャーナリスト・安田菜津紀さん@NatsukiYasuda 「小さな共感の積み重ねが大切。それは自分にも返ってくる」
— Choose Life Project (@ChooselifePj) April 21, 2020
コロナ禍の中、不安から生まれる排斥の言動。混乱時だからこそ共感が必要とされる理由は‥。中東などで難民問題の取材を続けている安田さんの言葉です。#コロナ時代を生きるために pic.twitter.com/CmYzcxX9tD
岐阜市 准看・看護学校等受験対策個別支援 ~「申込書」ができるまで~

~支え続けるために~
岐阜県ひとり親家庭等就業・自立センターから、令和2年度就業支援講習会申込書類が届いた。
http://shien-gifu.sakura.ne.jp/koushu.html#moushikomi
塾に来られた岐阜市内のシングルマザーの方に、手渡すものとなる。
この「申込書」ができるまでには、多くの方の想いが込められている。
この申込書ができる流れは、2018年度に遡る。
ひとりの市議会議員さんからの提案から始まった。
http://haranahoko.jp/wp-content/uploads/2019/04/99274441c22769dd11e170754ec39914.pdf
市議・はらなほこさんは、私も赴任したことのある岐北中で人権教育を受けられた方だった。
「岐阜市ひとり親家庭等実態調査」の結果は、以下通りだった。
https://www.city.gifu.lg.jp/secure/40747/hitorioyatyousakekka%20_s.pdf
議員の質問通り、資格を取れる環境づくりが必要となる。
次年度、岐阜市長の政策決定を元に、担当課の方が精力的に企画づくりをされた。
上の実態調査26ページには「取りたいと考えている資格」が書かれている。
パソコン・介護福祉・ホームヘルパー・医療事務・看護師の順に並ぶ(その他を除く)。
そのうち上位4つについては、岐阜県ひとり親家庭等就業・自立センターの講習会で学ぶことができる。
http://shien-gifu.sakura.ne.jp/Brilliant/center-dayori2.pdf
そこで岐阜市は、5位・104人の希望者がいる看護師の資格取得支援をすることとなったようだ。
准看護師・看護師の資格を取得するには、必ず学校に入学しなければならない。
入学後の支援は、各市町村で行われている。となると、入学までの支援を行えば資格に結び付けることができる。
岐阜市の担当者の方は、2019年に企画を練り上げ、2020年からの支援事業となるよう努力を重ねられた。
その申込用紙が今、私の手元にもある。私の塾がその委託先となっている。
岐阜市在住の方で希望される方は、岐阜県ひとり親家庭等就業・自立センターで申し込みができる。
http://shien-gifu.sakura.ne.jp/kousyukai-oshirase.pdf
岐阜市のシングルマザーの方は是非、そちらを通して准看護師・看護師を目指してほしい。
多くの方の想いが形となり、そして私にその実現を託された。バトンを受け取ったのだ。
私が今、この状況でも塾を開け続けている一番の理由はここにある。不安が消える場は、1つでも多い方がいい。
『心のケアって…今
— Akemi (@kemi7a) February 8, 2020
わかったわ
誰もひとりぼっちに
させへんって
ことや…』
#心の傷を癒すということ#最終話#安先生#柄本佑さん pic.twitter.com/APVsrZm030
そして岐阜市以外のシングルマザーの方は、私の塾のプロジェクトで例年通り支えていく。
明日、ブログで【第6期・シングルマザー看護奨学生募集】を発表する予定。
明日から、オンライン双方向授業へ ~大学遠隔授業を参考に~

~まずは、使いこなすことから~
明日から、岐阜聖徳学園高校オンライン双方向授業を開始できるよう準備に入る。
私が担当する生徒の皆さんには、Classi授業動画は先週配信済みになっている。
そして次々と、問題に対する解答結果が私の手元には集まっている。おかげで、
授業開始時に解説する内容も絞り込めた。その上で、本時の狙いに迫ることができそうだ。
岐阜県衛生第二看護学校では、このような『事前学習』をされていると聞いている。
准看護学校での学びを元に、教科書で『事前学習』をして、そのレポートを授業前に提出。
レポート内容を元に、授業をされる先生方は解説するという。理解度を確認してからの授業となる。
多くの生徒がわかっているところは解説を省略し、わかっていないところに重点を置く。効率的だ。
また、急遽遠隔授業となった大学の授業も参考になる。その中でも一番、
私が参考にしているのは、岐阜女子大学1年生の遠隔授業だ。
さすが「面倒見のいい大学・全国1位」として有名な大学ならではの動きを感じる。
不慣れな遠隔授業に対して、担当の先生方が不安を解消する動きを見事にされている。
今回、私が担当するのも1年生。条件も似ている。岐阜聖徳学園高校では先週、iPadの使い方講習が行われた。
iPadの使い方を教えてもらったばかりの状態だが、Classiに取り組めている生徒が多い。
Classiは昨日まで不具合もあったにもかかわらず、いい状況だ。
明日は「ロイロノートが使えるか」の確認を行い、オンライン双方向授業へと向かう。
まずは、機器に慣れ使いこなすところから。
高校生は私より、使いこなすことが早い。
前年度も私は、生徒からiPadの使い方を随分教えていただいた。
今年度もすぐに、そんな状況に変わっていくだろう。
事前把握から授業へ ~オンライン双方向授業の模索~

~次の手を、どう打つか~
今日も、来週からの岐阜聖徳学園高校オンライン双方向授業を模索している。
Classiのおかげで、授業動画は昨日までに配信済みになっている。
そして、動画に対応した問題が出題され、それぞれの解答結果がわかる。
各問題ごとの正答率がグラフ化されるで、授業前には理解度が事前把握できるだろう。
ここからどうするのか…考えているうちに30年前の記憶が蘇ってくる。
30年前、私は各務原市立那加中学校の教員だった。研究推進メンバーとして、
翌年の道徳全国研授業発表に備えていた。実際、翌年に私は授業発表者となった。
その時に取った手法は、「価値の事前把握」をして「話し合いを組織化する」というものだった。
そのため道徳授業は、2時間で1つの教材を用いていた。
1時間目は資料を読み、生徒に3つの設問をし、アンケート形式で回答させた。
2時間目までに教員はアンケートを基に、生徒の持っている価値を事前把握。
指名順と切り返しの発問を練る。「予想(期待)される生徒の反応」から本時の価値に迫った。
今の私の状況は、1時間目の道徳授業を終えた時に、よく似ているのである。
正答率は、事前に把握できている。
それに対し、教科書問題を用いて「自己評価活動を行えばいい」ことになる。
早く正解した生徒から、次の動画視聴・対応問題を解く時間に使ってもらえばいい。
また、ワークなどの定着・発展問題を解いてもらってもいい。
正答率が悪い問題に対しては、事前に補足説明をいれておく。
正答率が低い生徒には、ヒントとなるカードを準備する。
このように事前把握できた状況に対して、手を打つものを準備する。
授業時間が進むにつれ、私が対応する生徒数は減っていくことになる。
これが今、考えられる「次善の策」だ。
「ICT」+「少人数によるバズ学習」が、前年度は効果的だった。今年もそうしたかった。
しかし、今年度のオンライン双方向授業では、それは使えない。
なのでこの「次善の策」で対応する。授業が再開し、さらにバズ学習ができる状況になるまで「この流れ」となるかもしれない。
授業の前半が「本時」となり、後半が「次時の導入」となる変則的な授業で、生徒の理解を高めていくことにした。
先日、気になっていたクラウドファンディングが目標達成した。
最初期の目標200万円を突破しました。
— 平田オリザ (@ORIZA_ERST_CF) April 18, 2020
本当にありがとうございます。
この医療関係者と芸術家の連帯は、ウイルス禍収束後も、大きな財産として残っていくのではないかと思います。https://t.co/0QTPDfld8P
ネクストゴールに向けて、さらに支援が増えることを願いたい。